パーキンソン病
<病気のこと>

パーキンソン病とは?
1)発症原因・予後
50歳以上に多く、加齢に伴う神経の変性が主な原因です。脳内の黒質というところのドパミン神経細胞が減少することによって、体の調節がうまくいかなくなる進行性の病気です。また、進行性のため治ることはありません。
2)特徴的な症状
安静時振戦(ふるえ)、筋固縮、無動・寡動、姿勢反射異常(前かがみ、小刻み歩行)
3)その他の症状
便秘、認知機能低下、自律神経症状、不眠、流涎、うつ、多汗、嗅覚障害など
4)タイプによる予後
一般的に震えの症状が主なタイプは進行が遅く、筋固縮や動作緩慢の症状が主なタイプは進行が早いと言われています。また、幻視をともなう場合は、レビー小体型認知症の可能性もあるため注意が必要です。そのほかに、レポドパ製剤が効きづらい場合は、パーキンソン症候群(原因が他にあるもの)も考えられるため注意が必要です。
パーキンソン病の経過や段階
1)ハネムーン期(症状安定)
発症から3年~5年の間はハネムーン期といって、レポドパ製剤の効果を安定して得ることができます。
2)オンオフ現象・ウェアリングオフ(薬が効いていない)
ハネムーン期をすぎると、じょじょに薬の効きがわるくなり、次第にオンオフのはっきりした時間や症状が強く出る時間が出てきます。これは、ドパミン神経細胞が減少するために、貯蓄できるドパミン量が足りずに起きる現象です。
3)ジスキネジア・ジストニア(薬が効きすぎている)
長期間のレポドパ製剤服用により、ジスキネジアという手足が勝手にうごいてしまう症状が出現します。効果よりも副作用が強く出てしまっている状態です。
4)しだいに進行
症状はじょじょに片側から両側性となり、誤えん、転倒などを起こしやすくなります。全経過は15年から20年と言われていますが、適切なケアを行うことによって平均寿命に差があまり出ないことがわかっています。
パーキンソン病のケア
1)薬物療法
L-dopa(レボドパ)、 ドパミンアゴニスト 、抗コリン薬、塩酸アマンタジン、ゾニサミド 、アデノシン受容体拮抗薬、MAO-B阻害薬 、 カテコール-O-メチル転移酵素(COMT)阻害薬
2)運動療法
パーキンソン体操、嚥下体操、発語リハビリなど
3)鍼灸・マッサージ
鍼による症状緩和やマッサージによる拘縮予防
4)手術療法
深部脳刺激療法(DBS)
パーキンソン病
<当院の施術内容>
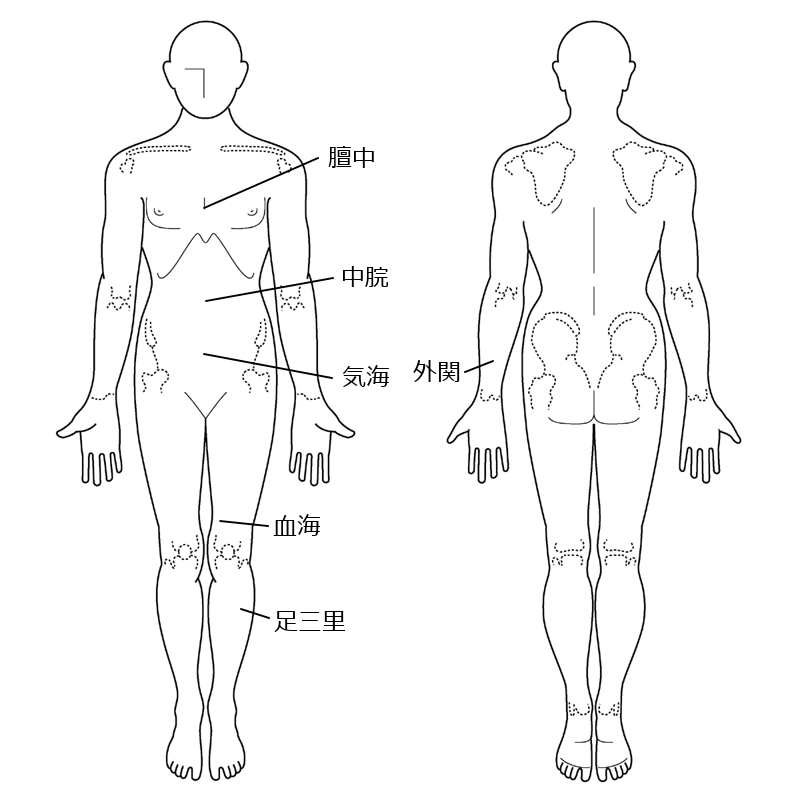
「益気調血・扶本培元(全身調整)」による抗老化
当院で使用しているツボ
1)主に使用するツボ:
三焦鍼法(さんしょうしんぽう)
1)外関(がいかん):三焦(五臓六腑)を総合的に整える目的で処方
2) 血海(けっかい):血(けつ)を整える目的で処方。
3) 足三里(あしさんり):気を補う目的で処方
4)気海(きかい):下腹部(下焦)を整える目的で処方
5)中脘(ちゅうかん):中腹部(中焦)を整える目的で処方
6)膻中(だんちゅう):胸部(上焦)を整える目的で処方
2)症状に応じて加えるツボ:
1)頭皮鍼震せん区:前頭部のツボ。ふるえ
2)廉泉(れんせん):のどのツボ。流涎、飲み込みづらい、舌のもつれ
3)委中(いちゅう):膝裏のツボ。足が前に出づらい
4)天枢、水道、帰来(てんすう、すいどう、きらい):腹部のツボ。便秘
5)四神総(ししんそう):頭頂部のツボ。精神的な症状
6)八髎穴(はちりょうけつ):仙骨のツボ。泌尿器症状
7)中極、関元(ちゅうきょく、かんげん):下腹部のツボ。泌尿器症状
特殊鍼法の解説
1)三焦鍼法
解説:三焦鍼法とは、天津中医薬大学第一付属病院の韓景献教授によって開発されたパーキンソン病や認知症など神経変性疾患に対して有効な鍼灸処方です。韓景献教授の提唱する「三焦気化失調ー老化相関論」に基づき、「益気調血・扶本培元」を目的として開発されました。基礎研究・臨床研究にて効果が裏付けされており、臨床応用されています。
2)研究動向
翻訳:三焦鍼法のパーキンソン病患者の運動機能と非運動機能改善の可能性が示唆された。中・軽度のパーキンソン病に対して、三焦鍼法は有効な治療手段となりうる可能性が示唆された。
参考文献:刘云鹤, 刘阿庆, 贾玉洁, et al. 三焦针法治疗帕金森病的疗效观察[C]// 2013中国针灸学会学术年会——第四届中医药现代化国际科技大会针灸研究与国际化分会. 0.
パーキンソン病
<当院の取り組み>
パーキンソン病に対する考え方
1)病気をなるべく進行させない
病気の進行をなるべく遅くして、豊かな生活を送れるようにする
2)症状をできるだけ改善させる
症状を緩和させて、豊かな生活を送れるようにする
鍼のメリット
1)副作用がない
鍼療法には副作用がほとんどありません。薬物療法や運動療法との相性もよく、相乗効果が望めます。また、多剤服用による副作用リスクも下げることができます。
2)新しいアプローチ
新しいアプローチを加えることによって更なる症状緩和や進行抑制が期待できます。
3)中枢(脳)への作用
鍼による刺激は、局所だけではなく、中枢(脳)へ作用することがわかっています。
4)局所への直接作用
神経や筋肉を直接刺激し、運動機能の改善が期待できます。
5)自律神経の機能調節作用
皮膚を介した自律神経反射を利用することによって、自律神経症状の改善が期待できます。
パーキンソン病ケアのポイント
1)進行性の問題
悪くなってから何とかすればよいと考えられる方がいますが、進行性のため悪くなった後からのケアでは大幅な改善は望めません。そのため、早期からのケアが重要となります。なるべく悪くさせないという考えが大切です。
2)症状が多岐にわたる
病気のイメージから、症状は”震え”だけだと考えている方が多いですが、運動症状だけではなく、認知症状や頻尿・便秘などの泌尿器症状も出現するため、ご本人だけではなく家族にとっても負担が大きくなる傾向にあります。そのため、症状緩和や進行抑制は重要となります。
3)ハネムーン期をすぎると症状や副作用が強くなる
ハネムーン期という名前のとおり、症状が安定する期間がありますが、全経過期間(15~20年)からみて、ハネムーン期(3~5年)はあまり長くないと言えます。倍以上の期間は症状や副作用へのケアを生涯行う必要があります。そのため、安定した期間を少しでも長くすることが重要となります。
4)痩せやすい
病状が進むと、消化能力の低下や便秘などが生じたり、嚥下困難や流涎によって食事量が低下したり、震えや筋固縮によって多量のカロリーを消費してしまうことなどで痩せていく方が多い印象です。とくに痩せていくにつれて疲れやすくなり、症状もつよくでてさらに食べられなるという悪循環が起きやすくなります。健康維持のためにも、日頃から三食規則正しくバランスのよい食事をとり、適度に運動をおこなうことが大切です。
5)転倒に注意
姿勢異常や不安定さが出てきたりすると転倒のリスクが上がります。パーキンソン病の特徴として、リズムをとることが難しくなるため、歩幅にあわせてシールを床に貼ったり、「1,2,、」と声に出してサポートする方法もあります。また、急な方向転換は足のもつれにつながるため、大きく弧を描くように歩きながら方向転換をするよう工夫が必要があります。そのほかに、シルバーカーや歩行器、杖などを使うのもおすすめです。遠方への外出時には状況にあわせて車椅子を使うことも移動ストレス軽減につながるためおすすめです。
6)レビー小体型認知症
ありありとした幻視が特徴的な「レビー小体型認知症」はパーキンソン症状を伴うため、よく「運動障害が先だとパーキンソン病」「認知症状が先だとレビー小体型認知症」と言われることがありますが、パーキンソン病の場合は認知症状は早期から出現することはまれです。パーキンソン病と診断されてからレビー小体型認知症の症状が早期から出る場合は「レビー小体型認知症」の可能性もあります。レビー小体型認知症の場合は、純粋なパーキンソン病に比べて薬剤過敏や薬物反応が不良の場合が多く、より進行が早い傾向(7年程度)にあり注意が必要です。睡眠中の大声や体動(レム睡眠行動障害)、抑うつ傾向が先行して出現することがあります。

