脳卒中後遺症
<病気のこと>

脳卒中とは?
1)発症原因
高齢者に多く、主に動脈硬化によって発症します。脳卒中には、脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血が含まれます。生活習慣病である高血圧、高脂血症、糖尿病、喫煙がリスクファクターとなります。
2)主な症状
① 片麻痺:障害部位と反対側にでる運動麻痺
② 顔面神経麻痺:額から下の表情筋麻痺
③ 視床痛:感覚障害に伴う特徴的な痛み
④ 失語:うまく話せない、話が理解できない
⑤ 血管性認知症(VaD):物忘れ
⑥ パーキンソン症候群:パーキンソン病に似た症状。震えや動作緩慢
⑦ 自律神経症状:便秘や尿閉、尿失禁など
⑧ 視野欠損:視界が狭まる
⑨ えん下障害:うまく呑み込めない
3)再発リスク
一度発症すると再発するリスクが高く、年間で20人に1人(5%)、10年間で半数(50%)が再発すると言われています。また、再発時のほうが症状がより重く、より複雑になります。
脳卒中の経過や段階
1)急性期
発症してすぐは、思うように体がうごかせない、力が入らない状態(弛緩性麻痺)が続きます。
2)回復期
時間が経つにつれて粗大な動きが出始めて、徐々に細かい動きができるようになっていきます。この時期から痙縮(つっぱり、筋緊張がつよい状態)が出始めます。また、弛緩している期間が長い場合は、遷延性弛緩性片麻痺と言われる状態で、回復の程度は限定されやすいと言われています。
3)後遺症期・維持期
180日を超えると病院での医療保険利用によるリハビリが終了し、介護保険利用による訪問リハビリや通所リハビリに切り替わっていきます。介護保険利用によるリハビリでは、訓練による機能回復よりも日常生活全般の機能維持が目的(社会との繋がりなど)になっていきます。
脳卒中のケア
1)薬物療法
再発予防のコントロールなど
2)運動療法
医療保険利用によるリハビリ、介護保険利用によるリハビリ
3)鍼灸・マッサージ
鍼による症状緩和やマッサージによる拘縮予防
脳卒中後遺症
<当院の施術内容>
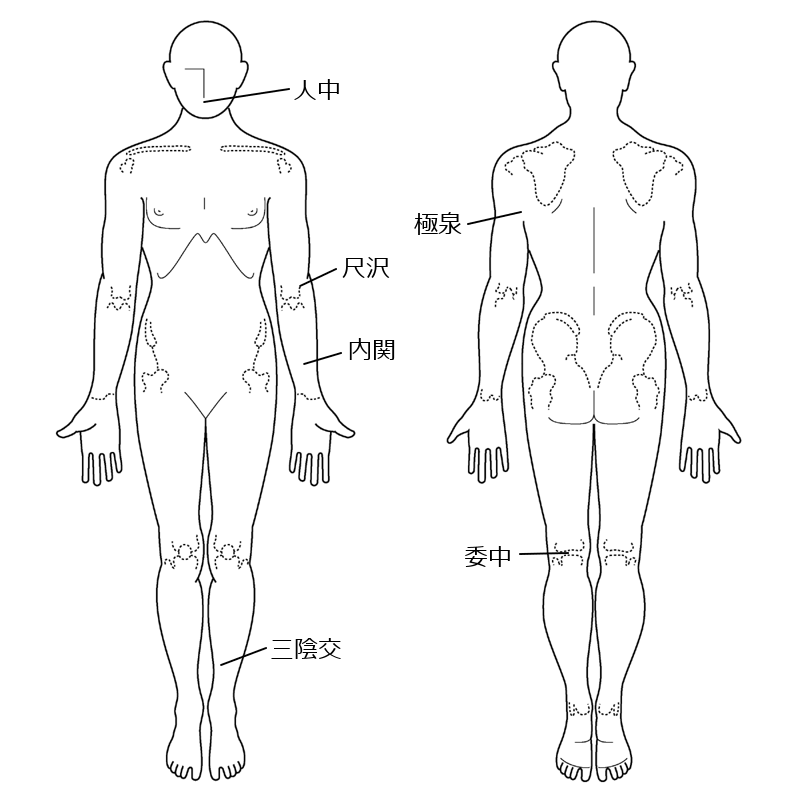
「醒脳開竅(中枢へのアプローチ)」による機能回復
当院で使用しているツボ
1)主に使用するツボ:
醒脳開竅法(せいのうかいきょうほう)
1)内関(ないかん):心肺機能を高める目的で処方
2)人中(じんちゅう):意識を覚醒させる目的で処方
3)三陰交(さんいんこう):肝腎を補う目的で処方
4)尺沢(しゃくたく):上肢の運動機能改善させる目的で処方
5)極泉(きょくせん):上肢の運動機能改善させる目的で処方
6)委中(いちゅう):下肢の運動機能改善させる目的で処方
2)症状に応じて加えるツボ:
1)合谷(ごうこく):手のツボ。手指の痙縮
2)廉泉(れんせん):のどのツボ。流涎、飲み込みづらい、舌のもつれ
3)太渓(たいけい):足のツボ。内反尖足
4)天枢、水道、帰来(てんすう、すいどう、きらい):腹部のツボ。便秘
5)四神総(ししんそう):頭頂部のツボ。精神的な症状
6)八髎穴(はちりょうけつ):仙骨のツボ。泌尿器症状
7)中極、関元(ちゅうきょく、かんげん):下腹部のツボ。泌尿器症状
8)陽明経(ようめいけい):手足の経絡。片麻痺
9)八風、八邪(はっぷう、はちじゃ):手足のツボ。指の弛緩や痙縮
特殊鍼法の解説
1)醒脳開竅法
解説:醒脳開竅法とは、天津中医薬大学第一付属病院の石学勉院士によって開発された脳卒中後遺症や神志病など脳病に対する鍼灸処方です。基礎研究・臨床研究にて効果が裏付けされており、臨床応用されています。
2)研究動向
① 脳出血と脳梗塞の2群間比較では統計学的有意差はみられなかった(P >0 .05) 。醒脳開竅法は脳出血、脳梗塞、仮性球麻痺にかかわらず効果を発揮し、有効率は98%を超えた。(下図参照)
参考文献:石学敏. "醒脑开窍"针刺法治疗中风病9005例临床研究[J]. 中医药导报, 2005, 11(1).
② 醒脳開竅法は視床痛患者の臨床症状緩和に有効であり、プレガバリン(リリカ)よりも効果が高い。また治療効果は一定しており、持続効果も優れている。そして、血漿β-EPの含有量の上昇、血漿SP含有量の低下作用が認められた。
参考文献:李雅洁, 田浩, 安丽, et al. 醒脑开窍针刺法治疗丘脑痛:随机对照研究[J]. 中国针灸, 2017(1).

脳卒中後遺症
<当院の取り組み>
脳卒中後遺症に対する考え方
1)早期から質の高い鍼を
時間の経過とともに治療成績は下がっていき、180日を過ぎると症状は固定されていくと言われています。質の高い、専門的な鍼施術を行っています。
2)症状をできるだけ改善し、機能回復をめざす
180日を超えても改善がみられる方はいますが、現行の医療保険制度では継続加療が出来ない仕組みとなっています。そういった方にも寄り添いながら、機能回復を目指しています。
3)健側ではなく、患側の回復をめざす
おもに、患側の機能回復を目的とした鍼施術を行っています。
4)麻痺肢だけではなく、中枢へのアプローチ
鍼刺激による脳機能回復を促し、症状の改善を目指しています。
ステージによる鍼の提案
1)急性期
回復の程度がもっとも期待できる期間です。中国では、発症直後(症状安定後)から、脳機能回復と脳の損傷予防を目的とした鍼を積極的に行っています。日本では、入院をしながらリハビリを行うケースが多く、なかなか鍼施術を受けることは稀です。
2)回復期
回復の程度がもっとも期待できる期間です。急性期と同様に、脳機能回復と脳の損傷予防を目的とした鍼を積極的に行っています。日本では、入院をしながらリハビリを行うケースが多く、なかなか鍼施術を受けることは稀です。ただ、状況的に可能であれば鍼施術を受けることをすすめています。
3)後遺症期、維持期
回復の程度が緩やかになる期間です。人によっては、まだまだ回復が見込めますが、180日を超えると、医療保険利用によるリハビリが受けられなくなります。中国では、後遺症期においても、機能回復と機能維持を目的とした鍼を行っています。日本においては、もっとも需要が高い期間です。維持期のとおり、患側を悪化させないことが重要です。
鍼のメリット
1)副作用がない
鍼療法には副作用がほとんどありません。薬物療法や運動療法との相性もよく、相乗効果が望めます。また、多剤服用による副作用リスクも下げることができます。
2)新しいアプローチ
新しいアプローチを加えることによって更なる機能回復や症状改善が期待できます。
3)中枢(脳)への作用
鍼による刺激は、局所だけではなく、中枢(脳)へ作用することがわかっています。
4)局所への直接作用
神経や筋肉を直接刺激し、運動機能の改善が期待できます。
5)自律神経の機能調節作用
皮膚を介した自律神経反射を利用することによって、自律神経症状の改善が期待できます。
脳卒中ケアのポイント
1)回復期のゴールデンタイム
ゴールデンタイムである”発症後180日”が大きな一つの壁となります。医療保険利用によるリハビリも終了となる分岐点です。そのため、ゴールデンタイム中に鍼治療が可能であれば、病院でのリハビリとあわせて積極的に受けることをすすめています。時間の経過とともに治療成績は落ちていく傾向にあるため、なるべく早い段階から質的量的に十分なケアが必要です。
2)後遺症期・維持期
介護保険による後遺症期・維持期のリハビリは訓練による機能回復目的ではありません。そのため、生活全般リハビリ(社会的なリハビリ)となります。機能回復が見込める場合や機能回復を強く希望する場合は、鍼施術をおすすめしています。また、動かさないことによる拘縮(固まる)や残存機能維持のためにも、機能回復、維持目的でのケアが重要です。
3)目標をもって治療にとりくむ
”完治する”という漠然とした目標よりも、段階だてた目標設定をすることが重要です。

